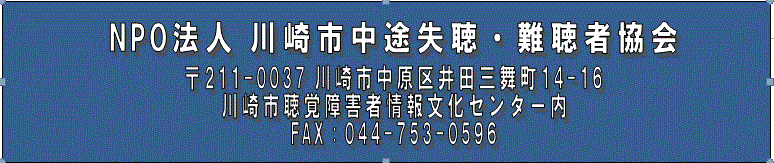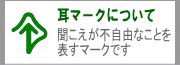![]()
|
|
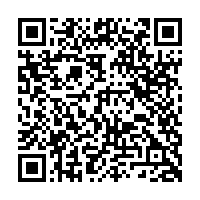 |
川難聴モバイルサイト |
川難聴 > 難聴者に分かる話の伝え方 > いろいろな会話の方法 (トータルコミュニケーション) |
いろいろな会話の方法 (トータルコミュニケーション) |
|
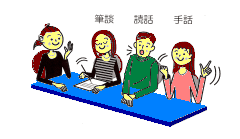 聞こえなくなる・聞こえが悪くなると、不幸のどん底に突き落とされたように思います。 しかし考えてみると、日常私たちは、手招きして相手を呼び寄せたり、手を振って別れたりしています。声を使わなくても、考えを伝えあっているのです。声だけが言葉を伝える手段ではありません。 聴覚障害者が言葉を伝える方法として、一番便利なのは手話です。手話は静かに話すこともできます。離れていても見えれば分かります。意味があります。ろう者は、「ろう文化」というように、文化と結びついた、優れた言葉です。しかし、急に英語で話すのが難しいように、難聴者が手話だけで話すのは難しいです。 日本語のアイウエオ・・・には、決まった口の形があります。これを見て言葉を読み取る「読話」という方法があります。大変便利です。練習すると、短い言葉は読み取れるようになります。しかし、長い文はうまくいきません。 補聴器は、難聴者の聞こえを助けてくれます。聞こえに合えば、静かなところの会話は、よくわかります。しかし大勢の集まりや屋外、街の中、車内の会話は、ほとんど聞こえません。難聴を完全には補ってくれません。 文字に書いて伝える筆談は、確実な方法です。しかし詳しく書くのは面倒です。 聴覚障害者が話を伝える方法は、いろいろありますが、一長一短があります。そこで手話だけとか、読話だけと限定しないで、あらゆる方法を利用します。手話、読話、補聴器、筆談、全部使うのです。そうすると、難しい手話が分からなくても、話が通じます。あらゆる話の方法を利用するので「トータルコミュニケーション」といいます。難聴者にあった方法です。 |
|